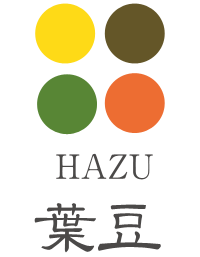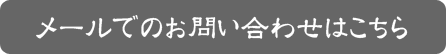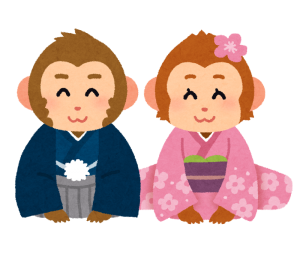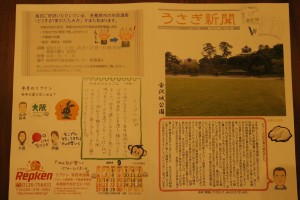桜の開花もほぼ平年並みで、今年は犬山祭や各務原桜祭りも
満開で迎えることができました。(^O^)/
いよいよ今月末からはGWになります。
GW中はもちろん休まず営業致します。
お待ちしております。m(_ _)m
葉豆の豆知識 No.017
紅茶編『美味しい紅茶の淹れ方』
前回は紅茶を美味しく淹れる為の水に関する情報でした。
今回は紅茶を美味しく淹れるポイントを幾つか解説致します。
①ジャンピング ジャンピングとは、ティーポットの中で起こる茶葉の
上下運動(対流運動)を云います。
茶葉がジャンピングする事によって茶葉の一片一片から
まんべんなく味や香りが抽出されます。
良いジャンピングをさせる為には、水の空気量、温度が最も重要です。
温度が低いと茶葉は浮き上がったままになり、高いと空気も少なくなり
茶葉は沈んだままになり泥臭くエグい紅茶になります。
ジャンピングをさせるポットはお湯の対流運動が起こりやすい
丸型のポットが理想です。ガラス製の物だと茶葉のジャンピングも
見ることが出来て最適です。
良いジャンピングを見ているだけでも高揚感や癒しなどの効果もあります。
②茶葉を蒸らす 茶葉の大きさで抽出時間は異なりますが、
2分〜5分ポットの中でじっくり茶葉を蒸らして下さい。
茶葉のジャンピングは約2分程続きその後はポット下に沈殿します。
③移し替え 茶葉を蒸らした後は、別のポットに茶葉をこして移し替えるか
ティーカップに注ぎきりましょう。
茶葉を入れっぱなしにすると濃くなり過ぎかつ余分な成分も抽出され
美味しくありません。
④保温 使用するポットやティーカップはあらかじめ温めておきましょう。
抽出中や抽出後のポットはティーコジーなどで保温して冷めるのを防ぎます。
『鵜沼茶坊 葉豆』では丁寧に淹れた美味しい紅茶を飲むことが出来ます。
珈琲豆リニューアル
四月より珈琲豆をリニューアル致します。m(_ _)m
①El Salvador(エルサルバドル)El Madrigado Estate
⇨⇨⇨ Cameroon(カメルーン)Caplami Java Longberry
②Indonesia(インドネシア)Alur Badak
⇨⇨⇨ Indonesia(インドネシア)Mandheung Toba-ko
③Tanzania(タンザニア)Mondul
⇨⇨⇨ Tanzania(タンザニア)Kirimanjaro Snow Top
④Kenya(ケニア)Red Mountain
⇨⇨⇨ Kenya(ケニア)Kenya Maasai AA
注)①Cameroon以外の原産地(国)は変更ありませんが、味や香りは違います。
詳しくはHPの珈琲メニューを参考にして下さい。
葉豆の珈琲ラインナップは中米4種類、南米2種類、アフリカ4種類
アジア他3種類となりました。
四月の定休日
葉豆の豆知識 No.016
紅茶編『紅茶と水の関係』
日本茶、台湾茶、紅茶など茶葉を使用する飲み物において
水が果たす影響は大きいものです。
その際、意識しておきたいポイントは「空気」「硬度」「温度」の3つです。
これらのポイントを押さえて淹れた紅茶は同じ茶葉を使用しても
ワンランク上の出来栄えになります。
①空気 水分中の空気が少ないと泥臭くエグミが出ます。
空気を多く含んだ水を作るにはポットに水を勢いよく注ぎ
水分中に多くの空気を含ませます。
汲み置きした水の場合、ペットボトルなどに入れ振って空気を含ませます。
②硬度 硬度とは水に含まれるミネラル含有量を表す数値です。
硬度が高いとドロリと重く、低いと香味が出過ぎてアンバランスになります。
同じ茶葉を使用しても硬水のイギリスと日本では水色や香味が違います。
ペットボトルのミネラルウォーターでもヨーロッパ産の物は硬水が多く
日本産の物は超軟水が多く両方ともに紅茶には不向きです。
幸いにして日本の水道水は軟水で紅茶に向いています。
カルキなどが気になる場合は浄水器をつけると良いでしょう。
③温度 水は沸騰させ続けると空気が抜けてしまいます。
必ず沸騰直前で火を止めます。
目安は水から強火で沸かし硬貨大の大きな泡が音を立てて弾け、
表面が波打って来た状態がベストです。
温度は98℃が適温になります。
水以外にも気をつけたいポイントは幾つかありますが、又後日……
『鵜沼茶坊 葉豆』では全て飲み物は浄水器を通した水道水を使用しています。
葉豆の豆知識 No.015
台湾茶編『台湾茶の分類』
中国茶の中に属される台湾茶ですが、
中国茶・台湾茶は分類上で発酵の仕方によって6種類に分けられます。
それぞれ緑茶、黄茶、黒茶、白茶、青茶、紅茶があります。
台湾茶は青茶に属するものが多く流通しています。
ご存知の通り台湾は中国より南に位置し
中央部には北回帰線が通り北部が亜熱帯性気候、南部が熱帯性気候になります。
さらに狭い国土には3,000m級の山脈があり高山茶という独自なお茶が作られています。
中国茶にはない高山茶を始め独自の発展を遂げた台湾茶
ここで代表的な台湾茶の数種類を簡単に紹介致します。
<<台湾四大銘茶>>
脂肪燃焼分解作用、新陳代謝を活発にする働き、便秘やむくみ解消、
メタボリックシンドローム対策など様々な生活習慣病の予防に効能があります。
効能だけにとどまらず、お茶としての香りや味は格別です。
①凍頂烏龍茶………台湾茶の中では最も有名、蘭やクチナシなどの
華やかな香りが変化し余韻が長く続きます。
②文山包種茶………発酵度が20%前後で緑茶に近い飲み口です。
ほのかな甘みと百合、ヒヤシンスの花の芳香
③木柵鉄観音茶……発酵度が40〜50%と深めの焙煎
ニッキと蜜の香りがする濃厚なお茶
④東方美人茶………発酵度が高く紅茶に近い飲み口になります。
味の決め手はウンカにかじられた茶葉を使うことです。
<<台湾高山茶>>
高山茶は標高の高い地域で栽培されるため、気温は涼しく朝晩は霧がたち込め
日照時間も短い環境下で成長します。
そのため苦味成分のカテキンが少なく、旨味成分のアミノ酸を多く含みます。
「高山気」と言われる突き抜けるような力強い花香が特徴です。
①杉林渓高山茶……南投県竹山鎮大鞍里 海抜800~1,700m
すっきりとした柑橘系の香りと味わい
②阿里山高山茶…….嘉義県梅山郷阿里山 海抜1,000~2,000m
すっきりとした清々しい味わい
③阿里山金萱茶……..嘉義県梅山郷阿里山 海抜1,000~2,000m
新品種の烏龍茶 独特のミルクやバニラのような香り
④梨山高山茶………台中縣和平郷梨山村 海抜1,700~2,400m
後味は桃や梨のような甘いフルーティーさ
⑤大禹嶺高山茶……..南投縣仁愛郷栄興村 海抜2,000~2,700m
濃厚なコクと滋味 喉に甘みが長く残ります。
『鵜沼茶坊 葉豆』では本国台湾の茶藝店でもなかなか飲む事ができない、
上記13種類全ての高級茶葉を用意しています。
初めてのお客様も台湾茶を飲んだ事のあるお客様も必ず満足して頂けると確信しています。
一周年記念と三月の定休日
<<一周年記念挨拶>>
謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます
さて 当店におきましては 開店以来 無事に一年が経過いたしました
こうして開店一周年が迎えられましたのは ひとえに
お客様のお陰と深く感謝しております
この機会に 一層のサービス向上を目指し
モーニングサービスを遅ればせながら始めさせて頂きます
それに伴い 営業時間と価格を見直しいたしました
今まで以上に一生懸命努力し美味しい飲み物を提供する覚悟でございますので
何卒 倍旧のご支援 御来店くださいますよう
心よりお願いして一周年のご挨拶といたします 敬具
<<一周年記念ウイーク>>
3月01日(火)〜3月07日(月)
御来店のお客様には葉豆の金券(有効期限なし)を差し上げます。
<<モーニングサービス>>
モーニングサービス実施にあたり営業時間を45分前倒しに致します。
モーニングサービス 9:15〜12:00
サービス内容
自家製カンパーニュ(田舎風フランスパン)のトースト
日替わり健康サラダ
茹で卵 with ヒマラヤ岩塩
手作りデザート(濃厚杏仁豆腐、コーヒゼリーなど)
<<価格改定>>
・コーヒー
本日の自家焙煎コーヒー 470円 ➡️ 450円
13種類のコーヒー 500円 ➡️ 480円
・台湾茶
日本茶玉露の約2〜8倍の価格の台湾茶
多くのお客様に飲んで頂ける様、破格の普及価格を続けて参りました。
より良い品質の台湾茶を飲んで頂く為、値上げさせて頂きます。
変更後価格に至っても本国台湾での価格よりも半額以下です。
詳しくはWEBメニューにてご確認願います。
3月09日(水) 定休日
3月16日(水) 定休日
3月23日(水) 定休日
3月30日(水) 定休日
葉豆の豆知識 No.014
珈琲編『コーヒー豆の焙煎』
珈琲は精製後(豆知識 No.5 参照)に出来上がったコーヒー生豆を煎ることによって、
コーヒー色した皆様のお目にかかるコーヒー豆になります。
生豆の特徴によって煎り具合が変わります。
煎り具合によってコーヒーの酸味、苦味などが決定されます。
焙煎度は大きく分けて以下の4種類が一般的です。
・浅煎り(Light roast,Cinnamon roast)
・中煎り(Medium roast,Hight roast)
・中深煎り(City roast,Full City roast)
・深煎り(French roast,Italian roast)
酸味が特徴のモカでも深煎りにすることによって、酸味は消え苦味が顔を出してきます。
逆に苦味が特徴のマンデリンでも浅煎りすると、酸味の強いものになります。
ただし生豆の特徴(品種、大きさ、硬さ、水分量など)によって適した焙煎度が
ありますので、生豆の特徴を活かした焙煎度を決める必要があります。
焙煎の方法も手網を使うものから、大型の焙煎機まで様々です。
コーヒー生豆を焙煎すると豆が膨張収縮して、はじける音がします。
この音をハゼといい、二回の音が違うハゼがします。
この二回のハゼ音を指標にして焙煎度が決定されます。
コーヒー生豆の品質もさることながら、生かすも殺すも焙煎によって大きく変わります。
『鵜沼茶坊 葉豆』では広く13ヶ国の良質な生豆を仕入れ、
10日前後で使い切る量を小型焙煎機で自家焙煎していますので、
いつも新鮮なコーヒーを飲むことができます。
珈琲豆変更のお知らせ
「鵜沼茶坊 葉豆」の珈琲豆が変更致しました。
①ブラジル
旧:Tomio Fukuda dry on tree ————> 新:Bourbon Amarillo Arco Iris
品種がムンドノーボ種からブルボンアマレロ種に変わりましたが、
両方とも完熟豆を使用しているので甘味は同等でコクが増した感じです。
②コロンビア
旧:Nabusimaque JAS organic ————> 新:Superemo Anjerica
品種がティピカ種からカトゥーラ種に変わりました。
甘味、渋味は少し増した感じです。
③グアテマラ
旧:Antigua La Soledad ————> 新:Antigua SantaBarbara
品種がカトゥーラ種からティピカ種に変わりました。
ややスッキリとした印象です。
④ニカラグア
旧:Casa Blanca Caturra ————> 新:Monimbo
独特なクセがなくなり飲みやすく感じられます。
珈琲豆や茶葉も少しずつ変わっていきます。
更に新しい出会いが待っています。m(_ _)m
葉豆の豆知識 No.013
紅茶編『紅茶の分類』
日本人の多くの方は、紅茶と云えば日東紅茶、リプトンなどの
ティーバッグで淹れる紅茶が一番馴染んでいると思います。
紅茶の名称としてアールグレイ、ダージリン、セイロンなども馴染みがあると思います。
しかしながら、それらの名称の意味は全く異なります。
アールグレイはフレーバードティーの名称であり
ダージリンはインド北部の紅茶の産地の地名で
セイロンは旧国名で現在はスリランカです。
紅茶の世界で混同しやすい用語をここで簡単に説明致します。
①ストレートティー……日本では砂糖、ミルク、レモンなどを入れない
紅茶をストレートティーと言います。
本場英国ではレモンティーはありません。
②エリアティー……単一産地の紅茶で他の産地とブレンドしていないものを指します。
同一産地でのブレンドはエリアティーに含みます。
コーヒーで最近使われているシングルオリジンと同じ意味です。
インド….ダージリン、アッサム、ニルギリなど
スリランカ….ウバ、ヌアラエリア、ルフナ、ディンブラなど
③フレーバードティー……茶葉に果実や花などの香りをブレンドしたものを指します。
香りのつけ方も茶葉にエッセンスを加えたもの、花びらや果実の皮を合わせたもの、
茶葉に香りを吸収させたものと様々です。
キーマン茶に柑橘系のベルガモットの香りをつけたアールグレイが
最も有名です。他にアップルティーなどがあります。
④ブレンドティー……複数のエリアティーを合わせたものを指します。
フレーバードティーは含みません。
⑤ブラックティー……あまり馴染まないものですが、
英国などでは茶葉を使った紅茶のことを指します。
ブレンドティーは含み、フレーバードティーは含みません。
『鵜沼茶坊 葉豆』ではインド5種類、ケニア1種類、スリランカ4種類、
中国1種類、ネパール1種類のエリアティーをストレートティー又は
ミルクティーで飲む事が出来ます。
バレンタインデーGIFT
葉豆の豆知識 No.012
日本茶編『日本茶に人生をかける』
2016年1月20日、東海地方でこの冬初めての積雪の中
岐阜大学にて講演会があり参加させていただきました。
岐阜大学グローカル推進本部・留学生センター共催
講演会「日本茶に人生をかける」
ースウェーデン人が語る日本茶の魅力ー

<講演会の様子>
講演者は岐阜大学日本語・日本文化研修コース修了生で
スウェーデン人初の日本茶インストラクターとなった
ブレケル・オスカルさん
現在は静岡県農林技術研究所茶業研究センター研修生とのこと
講演内容は一般向けで日本茶の魅力あれこれでした。
内容はもとより日本茶に対する情熱を強く感じさせられました。
将来はヨーロッパ全体に日本茶のPR、普及を目指されています。
『鵜沼茶坊 葉豆』では日本茶、台湾茶、紅茶、珈琲の4品目を楽しめます。
微力ながら各務原市でそれぞれのPR、普及が出来たらと再確認出来ました。
葉豆の豆知識 No.011
珈琲編『コーヒー生産国(アフリカ、その他)』
世界約60ヶ国で栽培されるコーヒーですが栽培品種は勿論のこと、
気候風土などにより味や香りは様々です。
今回は前回 No.008『コーヒー生産国(南米・中米編)』の続編になります。
①タンザニア(Tanzania)
日本ではキリマンジャロの銘柄で知られています。
赤道直下に近く雨季が二回あり収穫も二回行われます。
肥沃な火山灰土壌で栽培され、個性的で高品質なコーヒーを産出しています。
しっかりとした苦味とコク、柑橘系のフレーバー。
②エチオピア(Ethiopia)
日本ではモカの銘柄で知られています。
コーヒーのルーツとも云われています。
栽培される珈琲豆は原生種に近く小粒な珈琲豆が多く流通しています。
生産量の40%程度が国内消費されています。
シトラス系の香りとワインのような熟成感。
③イエメン(Yemen)
エチオピアと同じくモカの銘柄で知られていますが、
エチオピアはモカ・シダモ、イエメンはモカ・マタリと呼ばれています。
名前の由来はイエメンのモカ港から出荷されたことによります。
独特のモカフレーバーと呼ばれる、ワイン系の香気、すっきりとした味わい。
④インドネシア(Indonesia)
日本ではマンデリンの銘柄で知られています。
世界第4位の生産国ですが、高価なアラビカ種よりも
病害虫に強いカネフォラ種を多く生産しています。
珈琲豆の精製は生豆の状態で乾燥させるスマトラ方式と云う独特な
精製法で珈琲生豆は濃い緑色が特徴的です。
芳醇でトロピカルな香味、深いコク、キレのある苦味。
⑤パプアニューギニア(Papua New Guinea)
ジャマイカのブルーマウンテンコーヒーを移植したため
ブルーマウンテンコーヒーに近いバランスの良い珈琲が安価で楽しめます。
酸味の質が良くトロピカルフルーツ系のフレーバー。
この他インド、ベトナムなどがありますが、
やはり多くはカネフォラ種を生産しています。
『鵜沼茶坊 葉豆』では13ヶ国のコーヒーが楽しめます。
謹賀新年
葉豆の豆知識 No.010
日本茶編『日本茶を美味しく淹れる』
同じお茶の葉を使っても正しい淹れ方で頂くと、日本茶はより美味しくなります。
それには急須にお湯を入れた時の温度と時間が重要になります。
お茶の主な成分は渋みのカテキン、苦味のカフェイン、旨味や甘味のテアニンなどがあり
いづれの成分もお湯の温度が高くなるほど溶出しやすくなり
渋味のカテキンは低温では溶出されにくく、
苦味のカフェインは高温ならすぐに低温ならじわじわと溶出されます。
旨味のテアニンは低温でも短時間でよく溶出されます。
これらの特徴により低温で淹れると旨味や甘味が濃く渋味や苦味の薄いお茶になり
高温では渋味や苦味が増して全体的に強い味のお茶になります。
さらにお茶の種類によって成分量が異なります。
おおよその目安は
玉露上 3人分、茶葉:10g、湯量:60ml、湯温:50℃、時間:150秒
煎茶上 3人分、6g、170ml、70℃、120秒
煎茶並 5人分、10g、430ml、90℃、60秒
番茶 5人分、15g、650ml、100℃、30秒
焙じ茶 5人分、15g、650ml、100℃、30秒
お湯は沸かしたてを冷まして使用します。
ちょっとの手間で味は変わります。是非お試しあれ!
『鵜沼茶坊 葉豆』ではお茶を淹れる行為も楽しんで頂くため、
一煎目はスタッフが二煎目以降はお客様ご自身で淹れて頂きます。
葉豆の豆知識 No.009
日本茶編『日本茶の歴史』
日本茶の起源は中国から伝わったもので時期は不明ですが、
遣唐使の頃に行き来する僧などによって伝えられたと言われています。
鎌倉時代には抹茶文化が普及しお茶の栽培も広がっていきました。
もともと薬として飲まれていたお茶ですが、
南北朝時代から室町時代にかけて武士の間で産地銘柄などの利き当てを
競う「闘茶」や歌を楽しむ集まり「茶寄合」などが盛んに行われるようになりました。
安土桃山時代には千利休によって日本文化独特の茶の湯、茶道が完成しました。
江戸時代に入り広く庶民に飲まれるようになりました。
いつも通り、ありふれたと言う意味の「日常茶飯事」と文字通りなったのは
江戸時代以降となりますネ!
さて現在ではペットボトルのお茶を飲む人が増え、
急須でお茶を淹れて飲むことも減っているそうですが……
『鵜沼茶坊 葉豆』では玉露や上級煎茶など6種類の日本茶を
常滑焼の一点物急須で楽しむ事ができます。
たまには日常茶飯事でない、ひと時をお過ごし下さいませ。
葉豆の豆知識 No.008
珈琲編『コーヒー生産国(南米・中米編)』
世界約60ヶ国で栽培されるコーヒーですが栽培品種は勿論のこと、
気候風土などにより味や香りは様々です。
今回はコーヒーの産地別の特徴を簡単に紹介致します。
①ブラジル(Brazil)
生産量は世界一、国内消費はアメリカに次いで第2位のコーヒー大国です。
国内規格のコーヒー豆の等級でNo.1はなくNo.2が最高級品になります。
ブラジル サントス No.2はプレミアムコーヒーの代表格ですが、
ブレンドコーヒーのベースとして使われることも多いようです。
国土が広大で生産される豆も多岐にわたります。
②コロンビア(Colombia)
ブラジル、ベトナムに次ぐ世界第3位の生産量を誇っています。
アンデス山脈の麓で栽培されます。
国のバックアップでスペシャリティコーヒーなどの高品質な豆も多く生産されています。
コーヒー豆の等級はスペイン語のスプレモが最高級品になります。
③グアテマラ(Guatemala)
平地から高山地帯の広い範囲で栽培され、
伝統的製法から生まれる個性豊かなコーヒーを数多く生産しています。
SHB(ストリクトリーハードビーン)が最高級品になります。
④ジャマイカ(Jamaica)
日本ではブルーマウンテンコーヒーが高価なコーヒーとしてあまりにも有名です。
英国王室御用達と宣伝効果で高値で取引されていますが…….
高値で取引されているのは日本だけのようです。
⑤パナマ(Panama)
オークションでパナマエスメラルダ・ゲイシャが
最高落札価格を記録して一大ブームが起こりました。
なんとなくそそられる名前ですが芸者さんとは全く関係ありません。
コーヒー豆のゲイシャはティピカ系の栽培品種になります。
この他ニカラグア、エルサルバドル、コスタリカなど
個性豊かで良質なコーヒー豆の生産国があります。
『鵜沼茶坊 葉豆』では13ヶ国のコーヒーが楽しめます。
年末年始の営業日
葉豆の豆知識 No.007
紅茶編『紅茶の生産地』
北緯25度から赤道を挟んで南緯25度までをコーヒーベルトと云い
広く世界でコーヒーが栽培されています。
紅茶も同様にティーベルトがあります。
北緯45度から赤道を挟んで南緯35度まで
北緯45度は北海道の稚内の南あたりになり、
南緯35度はオーストラリア大陸をほぼカバーします。
コーヒーより広い地域で栽培が可能なお茶の木は、
中国種とインド種(アッサム種)の基本2種類に大別できます。
中国種はインド種の約半分の大きさで色は濃く葉先は丸みがあります。
寒さに強く緑茶に向く種ですが、ダージリン、キームンは中国種です。
インド種(アッサム種)は中国種の2倍の大きさで、
色は淡い緑色で葉先は尖っていて表面はデコボコしています。
寒冷地では育たず熱帯産が多いようです。
強い日光を浴びることで紅茶独特の渋味となるタンニンが作られます。
主な生産国は生産量順にインド、ケニア、スリランカ、インドネシア、中国になります。
中国は茶葉生産量は世界一ですが紅茶以外のお茶になる比率が高いため一位ではありません。
『鵜沼茶坊 葉豆』ではインド5種類、ケニア1種類、スリランカ4種類、
中国1種類、ネパール1種類の紅茶を飲む事が出来ます。
葉豆の豆知識 No.006
台湾茶編『台湾茶の収穫』
亜熱帯気候の台湾では一年を通じてお茶の収穫がされていますが、
収穫する季節や気候によって香り味わいに違いが生じてきます。
雨季ではお茶が淡白な味になり、寒い時期では濃厚な味になります。
日本茶と同じく一番茶(春茶)がやはり高価とされていますが、
平坦地と高山では芽吹きの時期(春)は違います、
さらに茶樹の年齢や日照など様々な要素が関わってきます。
一般的に夏、秋、春と冬の順で価格が上がります。
安価な夏茶はお土産店や免税店などで扱われることが多いようです。
良質なお茶の条件は以下の通り
①収穫時期:春または冬
②標高:高
③茶樹:若
④気候:晴れ、低湿度
これらの条件を満たした茶葉を高い製茶技術を持った茶師によって
美味しい台湾茶が出来上がります。
『鵜沼茶坊 葉豆』では本国台湾の茶藝店でも飲む事ができない、
高級茶葉を沢山用意しています。
初めてのお客様も台湾茶を飲んだ事のあるお客様も必ず満足して頂けると確信しています。
葉豆の豆知識 No.005
珈琲編『一杯の珈琲ができるまで』
お茶もコーヒーも飲み物として人の口に入るまで様々な工程があります。
今回はコーヒーの栽培から一杯のコーヒーになるまでを簡単に紹介します。
①栽培
北緯25度から赤道を挟んで南緯25度までをコーヒーベルトと云い
広く世界でコーヒーが栽培されています。
北緯25度は台湾あたりに、南緯25度はオーストラリアの中心地あたりになります。
さらに熱帯、亜熱帯地域の山岳地帯で降雨量の多い地域が適します。
ジャスミンのような白い花を咲かせコーヒーチェリーを実らせます。
②収穫
コーヒーチェリーの中に二つの種子が向かい合って入っています。
その種子を取り出してコーヒー豆を作ります。
③精製
コーヒーチェリーには外皮、果肉、内果皮、銀皮(種子を覆う皮)、種子
からなり、種子だけを取り出す方法として大きく2つの方法があります。
⑴ナチュラル(自然乾燥式)
果実を天日乾燥させて果肉を除去した後、固くなった外皮を脱穀します。
香味、味わいは深いが品質面でやや劣ります。
⑵ウォッシュト(水洗式)
機械を使って果肉を除去した後、発酵させて大量の水で洗います。
やや酸味のあるクリーンな味わいで品質も良いが、豊富な水資源が必要です。
最近では両者の良い所を取り入れた精製方法など様々です。
④焙煎
精製後に出来上がったコーヒー生豆を煎ります。
生豆の特徴によって煎り具合が変わります。
焙煎度は大きく分けて以下の4種類が一般的です。
・浅煎り(Light roast,Cinnamon roast)、
・中煎り(Medium roast,Hight roast)
・中深煎り(City roast,Full City roast)
・深煎り(French roast,Italian roast)
煎り具合によってコーヒーの酸味、苦味などが決定されます。
焙煎後3日目から10日目位が良いとされていますが‥‥
浅煎りの場合、酸味が目立ちますが煎りが深くなるにつけ苦味が顔を出してきます。
⑤焙煎豆を挽く(ミル)
抽出方法によって挽き具合が変わります。
・細挽き:エスプレッソ、エアロプレスなど
・中挽き:ペーパードリップ、ネルドリップ、サイフォンなど
・粗挽き:ウォータードリップ、フレンチプレスなど
⑥抽出
抽出方法によって同じ豆でも味や香りは変わってきます。
さらにお湯の温度、抽出時間などによっても変わります。
その他、細かな要素はありますが①〜⑥の工程によってコーヒーの味、香りなどが
決まってきます。
『鵜沼茶坊 葉豆』では広く13ヶ国の良質な生豆を仕入れ、
少量づつ自家焙煎を行い最良の状態を保ちつつ3種類の抽出方法で
一杯の珈琲を丁寧に提供しています。
葉豆の豆知識 No.004
珈琲編『珈琲の歴史』
コーヒーの起源はアフリカ大陸のエチオピア説と
アラビア半島のイエメン説があります。
両国はスエズ運河のある紅海を挟んで対岸の隣国になります。
いづれもしてもイスラム教の修道士が厳しい修行の疲れを癒し、
精神の覚醒に役立てたとされています。
イスラム教寺院で門外不出の秘薬、霊薬として長く飲まれていました。
豆を煎って飲むようになったのは13世紀頃とされています。
広く世界で飲まれるようになったのは17世紀でお茶の伝搬より少し早いのです。
エチオピア産コーヒー豆もイエメン産コーヒー豆も共に皆様にも聞き覚えのある
モカコーヒー(Mokha Coffee)と呼ばれています。
イエメン産はモカマタリ(Mokha Mattari)
エチオピア産はモカシダモ(Mokha Sidamo)などが有名です。
これは現在イエメンにあるモカ港から出荷された事からモカと呼ばれています。
両国のコーヒー豆はアラビカ種の原種が多く、
豆は小粒でコーヒーにすると独特の酸味があります。
『鵜沼茶坊 葉豆』ではイエメン産はMokha Mattari Classic
エチオピア産はYirgachefe G1 Naturalの銘柄コーヒーを飲む事ができます。
葉豆の豆知識 No.003
紅茶編『紅茶の等級』
オレンジ・ペコ(Orange Pekoe)と言う単語を見たり聞いたりした事はありますか?
紅茶の世界ではよく使われる単語ですが紅茶の茶葉の等級を表します。
トワイニング紅茶にオレンジ・ペコと言う商品名の紅茶があったりする為、
間違って理解してる人も多くいらしゃる様です。
勿論、オレンジの香り、味とは無縁です。
オレンジ・ペコとは紅茶の茶葉の等級を示す上位のランクになります。
主な等級は以下の通り。<wikipediaより>
・オレンジペコ (Orange Pekoe, OP)
茶葉の形状としては一番大きい茶葉を指す。
・フラワリー・オレンジペコ(Flowery Orange Pekoe, FOP)
オレンジペコ等級並の大きさの茶葉で芯芽や若葉が多く含まれるものを指す。
・ブロークン・オレンジペコ(Broken Orange Pekoe, BOP)
オレンジペコと同じ茶葉を細かく砕いたものを指す。
・ペコ(Pekoe, P)
BOPよりやや大きく、OPやFOPより小さい茶葉を指す。
・フラワリー・ペコ(Flowery Pekoe, FP)
Pで芯芽を多く含むものを指す。
・ブロークン・オレンジペコ・ファニングス
(Broken Orange Pekoe Fannings, BOPF)
BOPよりさらに細かくなった茶葉を指す。
・ダスト(Dust)
一番細かく粉状になった茶葉を指す。
ダストだからといって低級品というわけではなく、
上質なものから低質なものまで様々である。主にティーバッグに使われる。
・ファニングス(Fannings, F)
BOPFをふるいにかけたもの。Dより大きい。
・ブロークン・ペコー(Broken Pekoe, BP)
Pをカットしたもので、BOPより大きいサイズ。
・ペコースーチョン(Pekoe Souchong, PS)
Pよりも堅い葉からなる。香りも水色もPより弱い。
・スーチョン(Souchong, S)
PSよりも丸みがあり、大きくて葉は堅い。
・ブロークン・ペコー・スーチョン(Broken Pekoe Souchong, BPS)
PSの茶葉をカットし、ふるいにかけたもの。BPより大きい。
その他 OPより上級を示しアルファベットの冠が多く付いたものがあります。
国際的なルールは無く、主にインドの紅茶に使われている様です。
・ゴールデン・フラワリー・オレンジ・ペコ
(Golden Flowery Orange Pekoe, GFOP)
FOPのうち、チップを含み水色が美しい黄金色を呈すもの。
goldenはチップの色と水色双方を意味する。
・ティッピー・ゴールデン・フラワリー・オレンジ・ペコ
(Tippy Golden Flowery Orange Pekoe, TGFOP)
GFOPのうち、チップの量がとても多いもの。
・ファイン・ティッピー・ゴールデン・フラワリー・オレンジ・ペコ
(Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe, FTGFOP)
TGFOPのうち、ほとんどがゴールデンチップから成るもの。
・シルバー・ティッピー・ゴールデン・フラワリー・オレンジ・ペコ
(Silver Tippy Golden Flowery Orange Pekoe, STGFOP)
TGFOPのうち、ほとんどがシルバーチップから成るもの。
STGFOPもスペシャル・ティッピー・ゴールデン・フラワリー・
オレンジ・ペコと表示される場合がある。
・シルバー・ファイン・ティッピー・ゴールデン・フラワリー・オレンジ・ペコ
(Silver Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe, SFTGFOP)
ここまで来ると何が何だか分からなくなってきますネ。
これらは茶葉の大きさの等級であって品質の良し悪しではありませんが、
OP以上のものは手摘みで丁寧な仕事を要します。
同じ農園から出荷される紅茶でも収穫時期や場所など様々な要素と
テイスティングによって品質が決定します。
『鵜沼茶坊 葉豆』でも、いっぱい冠の付いた紅茶を飲む事ができますヨ!
葉豆の豆知識 No.002
台湾茶編『台湾の高山茶』
ここで言う台湾茶とは台湾のお茶の樹から茶葉を摘み加工されたものを言います。
近年のお茶ブームで台湾茶として売られているものの中には中国産やベトナム産が
多くなってきています。
台湾のお土産店や免税店などで購入した台湾茶は残念なことに偽物の台湾茶で
あることもあります。
台湾で台湾茶を購入する際は、信用のおける茶行で試飲して購入する事を
おすすめします。
台湾では烏龍茶、包種茶、紅茶、緑茶を作っていましたが、
1980年代に入り台湾独自の高山茶が誕生しました。
高山茶は標高1,000m以上で産するお茶を言います。
中でも大禹嶺高山茶は標高2,600m(世界最高)で栽培されています。
亜熱帯気候に属する台湾には3,000m級の山脈があり、寒暖差と霧、温度と湿度、
肥沃な土壌など様々な恵まれた気候風土によって作られます。
高山で栽培されたお茶には特有の香気と滋味があり飲んだ人を魅了します。
台湾高山茶の代表的なもの
・阿里山高山茶
・杉林渓高山茶
・梨山高山茶
・大禹嶺高山茶
など
台湾四大銘茶
・凍頂烏龍茶
・木柵鉄観音
・文山包種茶
・東方美人茶
『鵜沼茶坊 葉豆』では上記全ての台湾茶を飲む事ができます。
葉豆の豆知識 No.001
お茶編『お茶の起源と種類』
お茶の起源は中国雲南省付近で、お茶には薬用効果があり、
不老長寿の霊薬としての神秘性が重視され宗教と結びつき、
一般的な飲み物となる前に宗教的、政治的、儀式的なものとなり
禅や茶道に発展してきました。
お茶は中国周辺の国々から17世紀に入りヨーロッパに渡り世界中で
飲まれる様になりました。
お茶は加工の方法により様々な種類があります。
中国では緑茶、白茶、黄茶、青茶、紅茶、黒茶6種類に大別されます。
世界的に知られているのは、酸化発酵をした紅茶としない緑茶が有名です。
同じ茶の樹から作られるお茶ですが酸化発酵100%のものが紅茶となり、
0%のものが緑茶となります。
その中間が白茶、黄茶、青茶、黒茶になります。
日本で知られてる烏龍茶や台湾高山茶などは青茶に、プーアル茶は黒茶に属します。
6種類の他にも中華料理でよく出てくるジャスミン茶は花茶に分類されます。
お茶の味や香りは茶の樹が育った気候風土と製茶加工技術と
抽出方法などによって決まります。
緑茶の中の日本茶6種類
青茶の中の台湾茶9種類
紅茶の中のインド、スリランカ、中国、ケニヤのノンフレーバーティー12種類
それぞれ違うお茶の中のほんの一部を『鵜沼茶坊 葉豆』では提供しております。
葉豆で扱っている日本茶、台湾茶、紅茶、珈琲の
歴史、文化などの話題を中心としたコラムを連載いたします。
週一回程度の更新を目標に頑張ってまいります。
宜しくお願い致します。